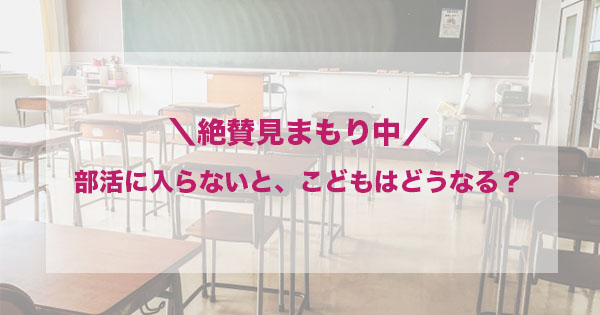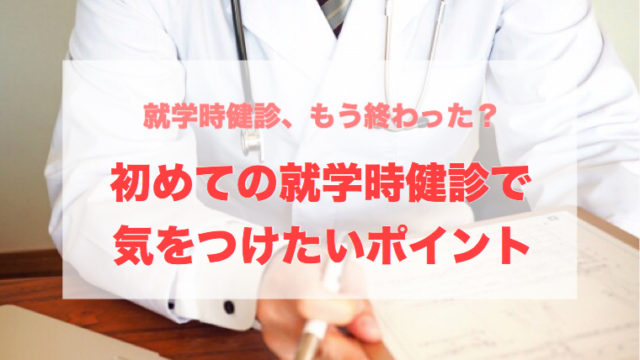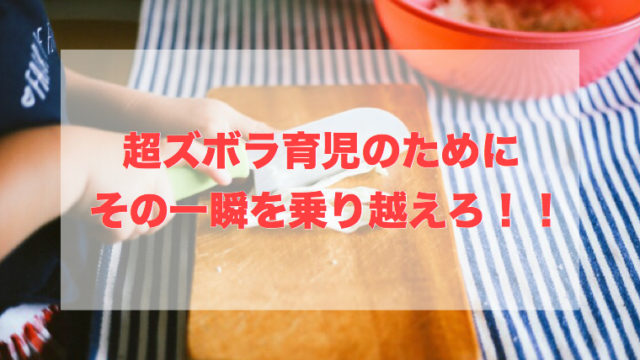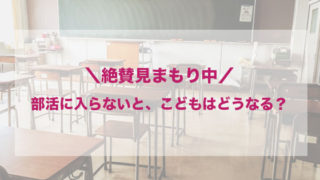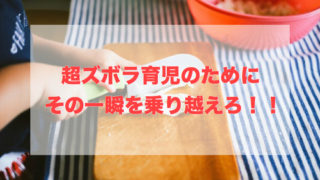Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xs536934/iikagenlife.com/public_html/wp-content/plugins/rich-table-of-content/functions.php on line 490
みなさん、ごきげんよう。まる◎です。
昨日、うちの長女が「胃腸炎」で学校を早退しました。
中学入学直後は学校があまり好きではなく、よくズル休みをしていた長女ですが、病気が原因の早退や遅刻は今までほとんどないのがチョット自慢です。
そんな長女が、久しぶりに“名前のある病気”が原因で、学校を休むことになりました。
しかし…… あまり症状がない。
…いや。胃痛はあるみたいだけど、それ以外は元気。
そこで今日は、「学校休んだ(早退した)けど意外と元気」だった場合の、まる◎流 “病気の治し方” をご紹介。「うちの子よく病気になるんだよね」という方も、ぜひ一度、まる◎流育児をお試しあれ。
学校を休んだら、好きなことしよう
病院で診察を受けたところ「軽い胃腸炎ですね〜。最近かかる人が多いんですけど、症状はかなり軽めなので痛みが治れば学校に行って大丈夫です。」と言われました。ホッ
病院を後にしてからの娘との会話はこうです
と、こんな話になったのですが「さすがに “胃を休める” 必要があるのにパンケーキはよろしくないのでは。胃にやさしい、うどんにしよう!」ということで話がまとまりました。
胃腸炎で学校休んだ長女と一緒に、おいしいうどん食べてきた😚
— まる◎育児2.0 (@SNS_mk) September 7, 2018
胃腸炎の時には、腹八分ではなく「腹五分」が良いらしいです。
そんなわけで蔦屋書店にきた📙
今日は本読むday。
— まる◎育児2.0 (@SNS_mk) September 7, 2018
いつも蔦屋書店に行くのは、休日がほとんど。
たまに平日に来てみると、意外な発見があったりもしました。おもしろいです。
てか蔦屋書店の中のタリーズ、平日と休日だと店舗の広さが違う😳✨
休日は壁の外にも椅子を並べてるから、席数が増えてるということか!
その分、平日は壁の位置をずらしてタリーズ店舗内を広く使っているという。。なんか、すごっ✨
— まる◎育児2.0 (@SNS_mk) September 7, 2018
「休む」の本当の意味とは
「休」という漢字のなりたち、辞書にはこう書かれていました。
- 人が木によりかかる
- からだや心の疲れがなおるようにする
- 一時的にやめる
- 「やめよ」「なかれ」と読み、〜するなの意。禁止をあらわす。
出典:[三省堂] 新明解 現代漢和辞典より
それを私はこのように解釈しています。
- 親はこどもにとって、理由なく寄りかかることのできる「大木」である
- 心の疲れをとることが「なおる」の最初の処方箋
- 考えるのをやめて、心の声に従う
- 無理するな
そうはいっても今日は寝ていたい。そんな時の対処法
当たり前ですが、そんな時には
寝てください。
ここで言う「好きなこと」というのは、つまり「体の声に耳をかたむけて、素直に従う」ということです。これは子どもに限ったことではありません。
日頃から仕事や家事・育児に追われている私たち主婦も、家族を養うためにがんばって働いてくれる夫も、そして、本当は遊んでいたいのに週5で学校や保育園に通う子ども達も。みんなです。
まとめるとこうです。
やっぱり家で寝ていたいな… → 寝て!
なんか食欲ないな… → 食べなくてよし。水は飲もう。
早退したけどお出かけしたい → でかけよう!
“仕方がない” はクセになる。
毎日の生活の中で “仕方ないからやっている” ことって少なからずみなさんあると思うのですが、“仕方がないからやる” が続いたりたくさんあったりすると、自分の本当の声に気づきにくくなります。
自分の本当の声というのは、内なる声。つまり
本田圭佑さんでいうリトルホンダであり
矢沢永吉さんでいうヤザワのことです。
※あ。伝わりにくかったらごめんなさいw
- 自分は本当は何が好きで、今なにを食べたいのか
- 何をしている時に心地よさを感じて、今どうしたいのか
- 本当の本当は、今、何をしたいのか。
普段からこれらを意識している人は、病気になりにくいのではないでしょうか。逆に「えー、全然わからないや」という人には、ぜひこれらの質問をいつも自分に問いかけるよう訓練をしてみてください。最初はわからなくても、自分にウソをつかない勇気を持てば、だんだん「自分の声」が聞こえるようになりますよ!
病気にかかるのは、自分のことが見えなくなったサイン
つまり私は「病気になる最初のきっかけは、自分のことが見えなくなったサイン」だと考えています。
現時点で自覚がなかったとしても、いつもどおりノリノリで元気だとしても、そういったサインが現れている時にはきっと自分でも気づかないうちに無理をしていたか、少しキャパオーバーな状態だと気をつけるようにします。
<参考記事>
「笑い」でがんへの免疫力向上 大阪の医療機関が発表:朝日新聞デジタル
いいかげん育児のススメ
そんなわけで、このブログタイトルにもある「いいかげん」という言葉を、私はいつも大事にしています。
育児をしていると周りから色々なことを言われたり、それによって悩んだりします。
でも、本当にママがやるべきことは「育てなきゃ」と気負うことではなく、いつも子どもが寄り添える「大木(たいぼく)」であることだと思いませんか?
正解が何かなんて分からないし、巷で言われている「正解」はただのサンプルにすぎません。
- 今この時、わが子が望んでいることは何か
- 本当の意味で母がすべきことは何か
これをいつもいつも考えることを習慣にしていると、だんだん、自分が今(母として)何をしたらよいのかが見えるようになってきます。
子どもにだって弱みを見せていい
そうはいっても、ママだって疲れちゃうことってたくさんありますよねー。
なので私はいつも「お互いさま」と「いいかげん(良い加減)」を使いこなします。
疲れたら、こどもにだって「疲れたー」と嘆くし
途中で投げ出したくなったら「もうママだって、イヤになった」と言います。
本当に困ったわがままな母ですが、いつもこども達は助けてくれるのです。
立派な大木だって、雪が降り積もると根元から折れ曲がってしまうことがあるのと一緒で、そうなる前に、こども達に助けを求めたらいいのです。
小さな天使たちがわ〜〜〜っと、降り積もった雪を除けてくれますよ。
(たまに放置もされますが。)
まとめ
まだまだ “ いいかげん育児 ” 勉強中の私。
うちの病気の治し方は、「みんなが(こどもも自分も)笑顔でいられることをする」です。
これが本当に正しいかなんて全然わかりませんが、なんかいつも、良い方向に進んでいるきがするっていう、ただそれだけのことです。
「なんか、よくわからないけどそうかもしれない!」と思ったら、ぜひみなさんも実践してみてくださいね。
それでは、またね〜!