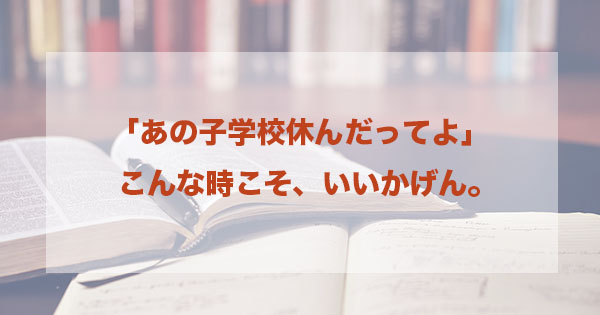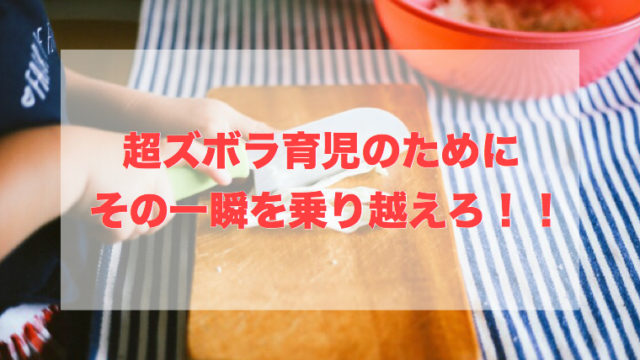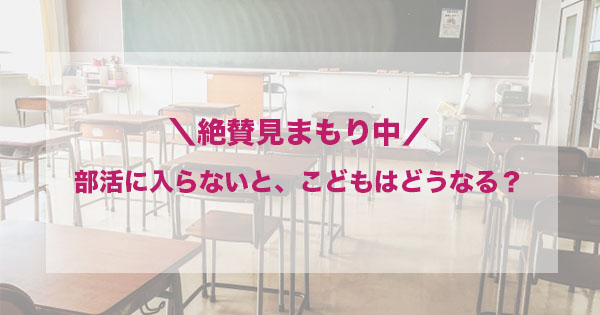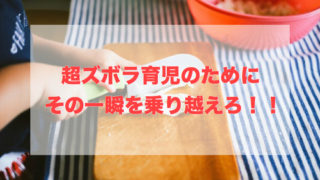Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/xs536934/iikagenlife.com/public_html/wp-content/plugins/rich-table-of-content/functions.php on line 490
みなさんごきげんよう。
いいかげん育児実践家のまる◎(@CA_926)です。
今日は末っ子の就学時健診(=就学時健康診断)でした。
私だけかもしれませんが、3人目ともなるとなにかと気が抜けます。
昨夜から「あ〜、明日は就学時健診だなー。準備しておかなきゃなー」と思っていた私ですが、結果、やらかしました。
就学時健診で末っ子があがる小学校に行ってきたのですが、
健診に必要な大事な書類を紛失したのは、まぎれもなくこの私です。
あ〜〜もう、だからちゃんと
前日に確認しとかなきゃ。気をつけてね、みんな🤣🤣🤣
— まる◎クソ真面目×いいかげん育児💫 (@CA_926) October 1, 2018
そんなわけで今日は、就学時健診を受ける際にやっておくべき準備や当日の注意事項などを、いちお元学校職員の私が「就学時健診の裏側」も踏まえてお伝えします(笑)
まずは健診表を事前に記入しておこう
そもそも就学時健診て何よ?という方のために、こちらをどうぞ
就学時健康診断(しゅうがくじけんこうしんだん)とは、初等教育に就学する直前に行なわれる健康診断である。就学時健診、あるいは就健と略される。
就学前年度の11月30日までに行なわれる。
つまり、小学校に入学するにあたって健康状態や発達状態などを、医師や専門家を通じて確認をする機会のことを言います。
事前に資料に目を通しておこう
受診できるのか分からなかったけど、受付終了時間が迫ってたからダメ元で学校に行ったよ😰
そしたらちゃんと予備が用意されてた🤓
意外と先生方の対応が慣れていて「あ、はいはい忘れね。これに記入して下さいね。」
って、もしかして忘れる人結構いるの⁉️😳相変わらずの母でごめんよ息子💦
— まる◎クソ真面目×いいかげん育児💫 (@CA_926) October 1, 2018
間違っても、私のように「やばい!失くした!!!」なんてことのないようにw
私は今回、受付日時にしか目を通していませんでしたが、事前に該当学区の小学校や市役所から届く資料を、ひととおり確認しておきましょう。
というのも、今回私は3度目の就学時健診だったのでなんとな〜く雰囲気や必要なものを把握していたため、手を抜きました。
しかしうちの子の学校では
- お子様の上履きをご持参ください(スリッパ不可)
- 当日の服装は、体操着のようなものが好ましいです
という注意書きがありましたが、保育園で上履きを使っていない我が家にとってこれは一大事。偶然にも昔いただいた上履きが眠っていたので、それを掘り起こして持参しましたw
また、資料には予防接種の受診歴など、母子手帳を見なければ分からない項目を記入することもあります。ゆとりをもって記入しておきましょう。
「早く受付をすれば早く帰れる」ではない
就学時健診は、基本的に受付をした人から子どもを小学生の児童に引き渡し、親は体育館などで講演や学校からの説明を聞くというパターンが多いと思います。
早く受け付けを済ませたグループは、健康診断が早くスタートします。
そのため「早く行けば早く帰れるのか〜」と思っているパパ・ママがいたら、一概にそうとも言い切れません。
就学時健診の重要ポイントは、服装にあり!
最後、こどもを引き取る時って何故か先に健診を受け始めたチームが後から帰ってくる現象あるけど、あれみんな、なんでか知ってるかな??
たぶんだけど、
チームの中にお着替えに時間がかかる子がいたからだと思うんだよね。着替えのスピードっていうより「着替えやすさ」ね。
たぶんだけど。
— まる◎クソ真面目×いいかげん育児💫 (@CA_926) October 1, 2018
その大きな理由は、この「服装問題」。
基本的に、健診には2園児につき1人程度の児童(5〜6年生)が手を引いて、該当の教室へ案内してくれます。
ただ教室へ連れて行ってくれるだけではなく、着替えが苦手な子のお手伝いをしてくれたり、順番に並ばせて混乱の起きないようにサポートをしてくれるのです。
しかし、早く健診をスタートしたのに遅く帰ってくるグループの中には、まれですが着替えにくい服を着ているために、着替えがスムーズにできない子が混ざっていたりします。
これが、最初に書いた注意書きの2つ目にあたります。
- お子様の上履きをご持参ください(スリッパ不可)
- 当日の服装は、体操着のようなものが好ましいです
この注意書きの意味は「脱ぎ着しやすい洋服で来てくださいね〜。その方がスムーズに進みますよ〜」ということなのです。
また、できるだけ重ね着をしないというのも、着替えをしやすくするポイントです。
もちろん慌てる必要はありませんが「自分のせいでみんなをいつも待たせている」ことが気になってしまうお子さんもいるので、服装については少し配慮するといいかもしれません。
待ち時間の子育て講話が思いのほか有益だった!
きのう台風とかやる事あって寝れなくて、健診行くまでの間ってホント眠いし疲れてるし
「あーだるいな。
就学時健診めんどくさいな。」と思ってたけど、子育て講話の中で突如はじまった周りの人とのワーク(子育てについて考える)が思いがけず楽しくて☺️
あ、来て良かったなと思った❣️
— まる◎クソ真面目×いいかげん育児💫 (@CA_926) October 1, 2018
到着後に渡される資料の中に、明らかに周りの人と一緒に何かをやる感じのものが含まれていて、孤独が大好きな私にはこの時間を耐えられるのか不安で仕方ありませんでした。
健診を終えて戻ってくる子どもを、ただただ静かに待っていたいのに。
待ち時間の講話の内容ってどんな感じ?
流れや内容はもちろん学校によって異なりますが、今回の場合、前半は学校から就学時健診の補足説明と、生活面や学費の引き落としについての内容説明があり、いよいよ後半、子育て講話がはじまりました。
講話の内容は、子どもが学校にあがってからの声かけの仕方だったり、シーンごとに「あなたならどのように対応しますか?」といったもので、各自の考えを周囲の方と共有するというワークが用意されていました。
私自身はわりと『いいかげん育児』が確立されている(と思っている)ので、最近ほとんど子育てで悩むことってないのですが、やはり初めてお子さんが小学生に上がるママたちは、なにかと不安があるようでした。
このワークでのママ達の意見は凄く興味深い内容だったので、また別の機会にまとめたいなぁと思いますが、初対面の方も含めたくさんのママと交流をもつ機会は、色々な発見があって非常に勉強になりました。
この機に「置き勉」について、先生に聞いてみた!

ワークが終了後も同じグループのママ達とは話が尽きず、会話の中で「そういえば、置き勉ってどうなんだろう。この子達が入学する頃には、置き勉できるようになっているかなぁ」という話題になりました。
分からないことはスグ聞く私なので、会場を片付けはじめていた先生に、こっそり質問をぶつけてみました。
<先生からの回答>
現時点では「全てを置いて帰る」ということは考えておらず、ちょうど今、全学年で置いて帰れる教材はあるか、それは何かを話し合っているところです。
次回の学校説明会までにはもう少し意見が固まると思うので、また次回ご説明させていただきます。
とのことでした。
小さな背中に十数キロの教材を背負うのはカナリの負担。とはいえ、手元に何も教材が残らないのも、宿題や自主学習にも困りますもんね。
実用的かつ効率的な結論が出ることを、期待したいです。
まとめ
いよいよ入学まで残り半年ほどとなったこの時期。
入学を控えているお子さんのママたちは、「1年生の壁」がどんなものなのか不安を抱えている方もおおいのではないでしょうか。
かくいう私も長女が入学の時にはドキドキの連続でしたが、こればっかりは経験してみないと分からないことばかり。
ママの緊張は子どもにダイレクトに伝わるので、ゆったりした気持ちで準備を整えましょう♪
それでは、今日はここまで〜。
最後までお読みいただきありがとうございました!